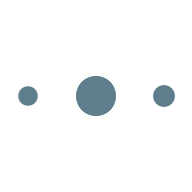檸檬・冬の日 – 他九篇
11篇の短編が収められている本。
作者は31歳で夭折したらしい。
僕は初めてこの作者の本を読んだが、文章は綺麗な表現で心を打たれるなと思った。
特に印象深かったのは表題作の「檸檬」、「冬の日」、それと「ある心の風景」、「冬の蠅」とかかな。
「冬の日」では冬至の頃の太陽の情景について描かれている。
冬陽は郵便受のなかへまで射しこむ。路上のどんな小さな石粒も一つ一つ影を持っていて、見ていると、それがみな埃及(エジプト)のピラミッドのような巨大な悲しみを浮べている。
(冬の日 p.67)
太陽高度が低くなった冬の日光がうまく表現されているなぁ。
なんとなく冬の日差しはせつない気分を感じさせる気がする。
青く澄み透った空では浮雲が次から次へ美しく燃えていった。
(中略…)
「こんなに美しいときが、なぜこんなに短いのだろう」
彼はそんなときほどはかない気のするときはなかった。燃えた雲はまた次つぎに死灰になりはじめた。
(冬の日 p.84)
冬の夕焼けの風景…
その光景の一瞬の美しさが感じられる。
作者は夕日の光景がけっこう好きだったみたいだな。
だが「冬の蠅」によると、それと同時に太陽に対する憎悪も持っていたという。
著者は病気で余命いくばくもなかったのだろうから、生の幻影を持つという太陽にそのような正反対の感情を抱くことも理解できる気がする。
「ある心の風景」では小さい鈴の描写が鮮明な印象を僕に与えた。
人びとのなかでは聞えなくなり、夜更けの道で鳴出すそれは、彼の心の象徴のように思えた。
(ある心の風景 p.63)
雑踏では聞こえない鈴の音が静かな場所では鳴りだし、その存在を認識させる。
そんな鈴が主人公の心の象徴だという。
私たちも人と一緒にいるより一人でいたほうが、自分の意識をより強く感じるもんな。
生れてから未だ一度も踏まなかった道。そして同時に、実に親しい思いを起させる道。
(中略…)
喬(たかし)は自分がとことわの過ぎてゆく者であるのを今は感じた。
(ある心の風景 p.63)
「とことわ」とは永久に変わらないことという意味であるらしい。
自分は永遠であると同時に移り変わってゆく者であるという相反する気持ちを主人公は感じたみたいだ。
なんともいい表現が続くなぁ…
この作者の文章を僕はけっこう好きかもしれない。
あとは、なぜか主人公の名前として「たかし」と名付けられた人物が多かったが何故なんだろう。
そして、本書は短編集だが、それぞれの物語につながりが感じられる気がした。
どの主人公も病気で療養中みたいだし。
解説に書かれていたが、作者自身結核に侵されていて、日々死の影と静かな絶望を感じていたようだ。
それが全ての作品を通して表されていたのだろうな。