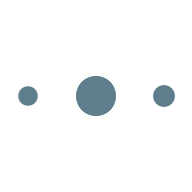フランスの詩人の作品。
パリの群集のなかでの孤独を半ば自伝的にしるした散文詩全50篇が収録されているという。
昔のパリの情景が浮かんでくるようだった。
僕の個人的な感想としてはけっこう読みやすかったかな。
特に前半部分がおもしろかった。
僕の印象に残ったのは、「老婆の絶望」、「芸術家の告白」、「剽軽者」、「愚人と女神」、「犬と香水壜」、「けしからぬ硝子屋」、「檻の中の女と気取った恋人」などなどだ。
「芸術家の告白」では秋の日の黄昏時の美しさ、自然の美について書かれている。
そして自然が芸術家を打ち負かすという。
今や天空の深さが私を狼狽させる、その清澄さが私を憤らしめる。
(芸術家の告白 p.14)
美の探究者である芸術家の悩みは深いんだな。
「剽軽者」では、新年の街中で、ロバに対しておどけて「よい新年を迎え給え! 」と帽子をとってお辞儀したある男について書かれている。
著者はこの男について、ものすごく腹立たしい気持ちになったらしい。
ムチで駆りたてられながら健気に働くロバは、この男に一瞥もくれず、ただ自分の義務を果たすため進んで行ったという。
「愚人と女神」では、ある道化役者について述べられている。
筆者は女神像の前で涙する彼の気持ちを推測するのだが、そのなかで彼をバカにする。
「この私は、人間の中の最もつまらない、最も孤独な、恋愛も友情もなくしてしまった、その点では、最もくだらない動物よりもなお遥かに劣った者です。」
(愚人と女神 p.24)
これには笑った。
道化師という存在は人から下に見られていたのかな。
「犬と香水壜」では香水の香りを気に入らず、糞便の匂いのほうを好む犬が民衆に似ていると言う。
これには考えさせられるな。
しかし、犬を犬ころと呼ぶのはどことなくかわいい。
あとは貧しい者と富める者の格差についていろいろ描かれていた印象を持った。
主人公である著者? がガラス売りをいじめていたずらをしたり、貧民に殴りかかったりするというちょっと過激な描写も出てくる。
まぁ、この詩に書かれていることが全て本当にあったことなのかは分からないけどな。